

湘南発、全国へ。2014年に葉山で始まったエンジョイワークスの分譲プロジェクト「エンジョイヴィレッジ」。これを全国に広げるべく、一昨年から各地の事業者とタッグを組んで、その地ならではの「ヴィレッジ」を展開しています。富山・御代田・佐久・岡崎・仙台…と、じわじわと拡大中。そのひとつ、宮城県石巻市の「石巻マリンヴィレッジ」を手掛けているのが、同県富谷市に拠点を構える株式会社あいホーム。「家を売るだけじゃなくて、まちを育てたい」。漁師やサーファーが行き交う港町・石巻に、「この場所だからこそできる暮らしの場」をつくり出しています。代表の伊藤謙さんに、家づくり・まちづくりへの思いと事業者目線でのヴィレッジの可能性についてインタビューしました。(聞き手:ENJOYWORKS TIMES・佐藤朋子)
──ひとまず、「エンジョイヴィレッジ」を知ったきっかけを教えてください
実は、東京の知り合いの経営者から「こういう場所(エンジョイヴィレッジを)、見ておいた方がいいよ」と勧められたのが始まり。その時は「へえ、そんな面白いプロジェクトがあるんだな」くらいの感じだったんですけど、しばらくして仙台の事業者さん(ユカリエ:ハロー! RENOVATIONなどでエンジョイワークスと協業している事業者)にも「一度見たほうがいいよ」と言われて。それで1年くらい前に、現地(葉山町内のヴィレッジ)を見に行くことになったんです。
初見でまず、“場所の使い方”に驚きました。区画整理された町なかに、象徴的な建物(スケルトンハウス)が建っていて。「え、こんなところにこんな家が?」って思ったのと同時に「この建物があるだけで、一帯の印象がガラッと変わるな」と感じました。つまり、“まちの魅力”って、建物ひとつで変化しうると気づいたんです。そこで「みんなで来よう」――と思いが膨らんで、社員を引き連れて再訪しました。
──現地を見て、「ヴィレッジ」という住まいや暮らしをどのように受け止めましたか?
「こういう暮らし方ならアリだな」とか「自分たちのまちにも、こういうのができたら面白いな」という気持ちになりました。いわゆる“住宅”というより、“まちの装置”というか、暮らしからまちづくりを考えるきっかけになる存在にもなり得るな、と。正直、(視察で訪れたのは)「こんな土地、検討もしないでしょ」と思うような変形地だったのですが、そこにすごく素敵な家が建っていて。「え?こんなふうに使えるの?」と、ある意味、衝撃でした。普通だったら、隣との間にフェンスとか塀を立てて「ここからここまでがウチです」って線を引きますよね。でも、そこには塀がなくて、隣の敷地と自然につながっている。敷地の一部を共有して、“境界”を引かないことで“関係”が生まれている感じ。これは、まちづくりとしてめちゃくちゃ新しいと思いました。
それから、エンジョイワークスの運営施設で「EAT LOCAL(イートロ)」のサービスも体験したのですが、その考え方にも強く共感しました。地元の食材を食べて、地元の自然や人と関わっていく。それって、地域に根ざして生きるためのベースになる思想だと思うんです。自分たちのまちにも、こういう価値観がもっとあっていいなと思いました。
──これを持ち帰って、「石巻でヴィレッジを」となったという訳ですね
僕たちは今、「マリンヴィレッジ」というプロジェクトを石巻で展開しています。漁師さんとかサーファーとか、海と関わりのある人たちを巻き込んで、住まいや暮らしのあり方を再設計しようという取り組みです。これは、湘南の「エンジョイヴィレッジ」と同じように、最初からお客さんと一緒に作るというスタンス。単なる“売り物”じゃなくて、プロセスそのものに参加してもらう形。今まで自分たちがやってきた「完成した分譲住宅を“売る”」のではなくて、一緒に“育てる”という視点を浸透させたいなと思っています。
現地では、6棟のスケルトンハウスを用意して、宿泊施設や賃貸、販売という形で動かしていく予定です。まだ全部が売れているわけではありませんが、行政からの問い合わせが来たり、「見学できますか?」って言ってもらえたりと、反応はすごくポジティブです。見学やお試しの滞在をした人たちは「比較するものがないけど、めっちゃいいですね」と前のめりな感想をくれて。過ごす時間が長くなると「こういう使い方もできそう」とアイデアがどんどん出てくる。この庭、みんなで使えないかな…とか。

完成している6棟。木貼り住居の「集合体」は、まちなかでも目を引く存在に
今年の初めにはこんなこともありました。釣りが好きな地元の人たちが「ヴィレッジで新年の釣り大会の打ち上げをしたら面白いんじゃない?」と言って、年明けの4日に実現したのです。そういうアイデアが自然に出てきて、すぐ実行できる。それがヴィレッジの良さかも。「ここにカフェがあったら、お店があったら」 「サウナが欲しい」みたいな声から、まちづくりに向けての横展開のヒントになっていく。そこには「まちを良くしたい」っていうメッセージがあって。もちろん自分たちは不動産として販売しなくてはいけないのだけど、「面白いからやっている」という雰囲気があるからこそ、広がり方が違うのだなと思っています。もう“住まい”というより“メディア”なんですよ。そういう空間がまちにあるだけで、周辺の土地も自然と売れていく。住まいや暮らしの意識が、まちに波及していくのだと思います。

釣りをしてヴィレッジに集まる。現代版「寄り合い」のコミュニティへの期待も
石巻マリンヴィレッジ
https://ishinomaki.enjoy-village.com/
──地域の不動産事業者として、地元での事業展開や「まちづくり」への思いを聞かせてください
あいホームの創業は宮城県の北西部にある加美町。実家は材木屋で僕は三代目です。大学を卒業してこの業界に入った際、正直なところ何も分かっていませんでした。20代はひたすら実務経験を積んでいたのですが、東日本大震災もあって、「自分に何ができるんだろう」と悩む時期が長く、当時は「歯が立たないな」という感覚が強かったです。でも、コロナ禍の時期に社長に就任し、会社の状況も木材の価格や流通といった業界の動きも大きく変わって、「このままじゃダメだ」とスイッチが入りました。そこからは、DX(デジタルトランスフォーメーション)も導入して、仲間と一緒に“もう一回勝負する”という覚悟でやっています。
オンラインやオフラインで人を繋げる仕組みを意識的に作り上げてきたのですが、その中で、エンジョイヴィレッジの事業は、「人々が集まる場所」としての重要性を改めて考える契機になっています。「点では良いことをやっている人がいるが、それぞれが繋がっていない」。それを橋渡しする場がなかったからかもしれません。ヴィレッジはそういう部分でも良い「仕掛け」になるものだと思っています。販売手法もチラシなどの販促から、口コミや紹介を活用した集客方法にシフトしましたが、「おもしろそうだから見てみたい」と言われるようになりました。こんな広がり方があるんだ、とお客さんからのアイデアや刺激があるのが嬉しいです。
僕は自分の会社で掲げている「最高のホームをつくる」という視点が、これから本当に大事になると思っています。単なる“建物”をつくるのではなくて、“ホームタウン”をどう作っていくか。つまり、地域そのものに愛着を持てるような場所づくりをしていくことが、僕ら地方のプレイヤーの役割だと思っています。ヴィレッジって、そういう意味で“装置”なんですよね。ただの集合住宅じゃなくて、人と人が出会って、混ざって、何かが生まれる場。こういうプロジェクトがあることで、「自分たちもやれるかもしれない」って思える。僕たちも、そんな希望をつなぐような場所を、自分たちの地域につくっていきたいと思っています。
あいホームウェブサイト
https://aihome.biz/
エンジョイヴィレッジウェブサイト
https://enjoy-village.com/

高性能でシンプル、内装はとことん自由な「スケルトンハウス」

2025/04/22
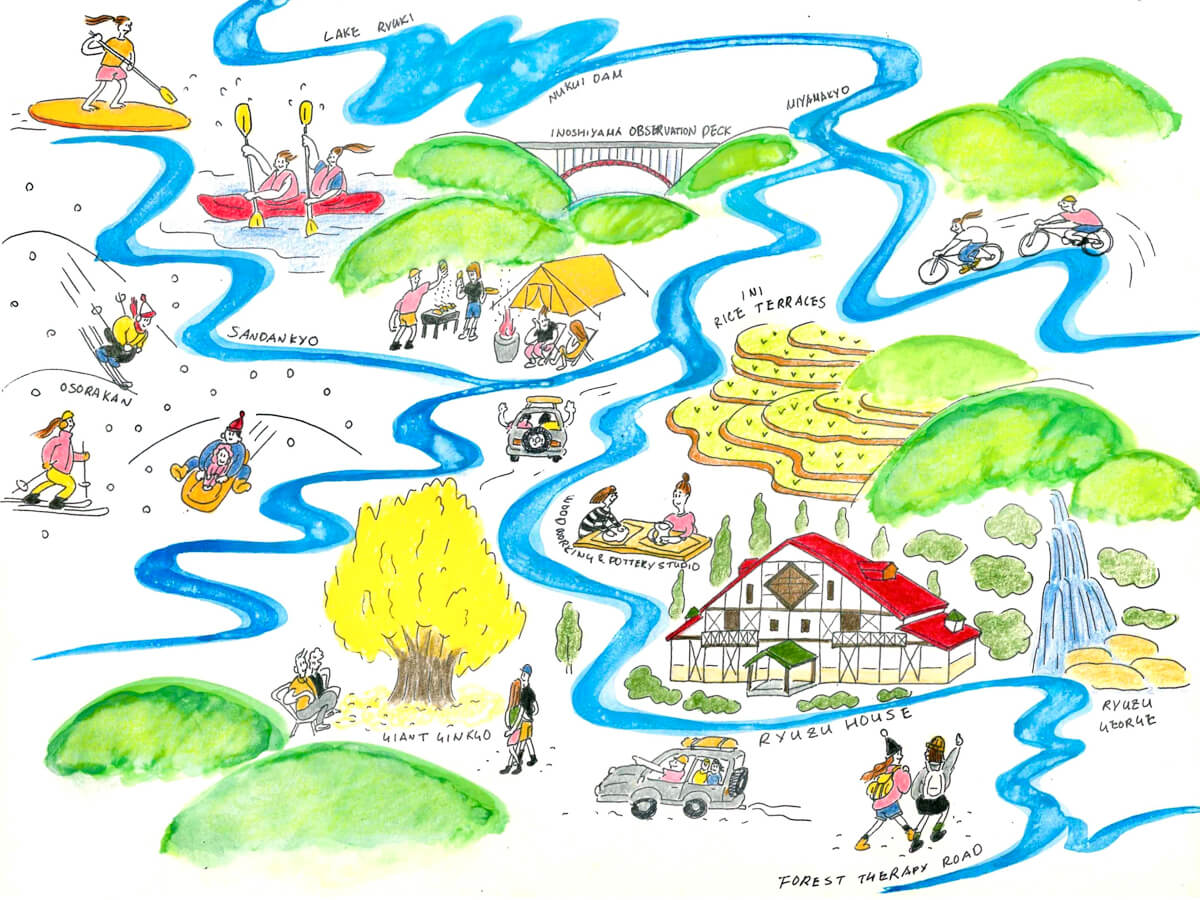
2025/05/06
